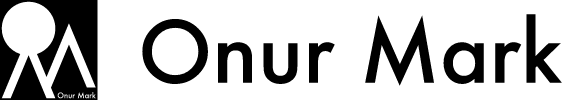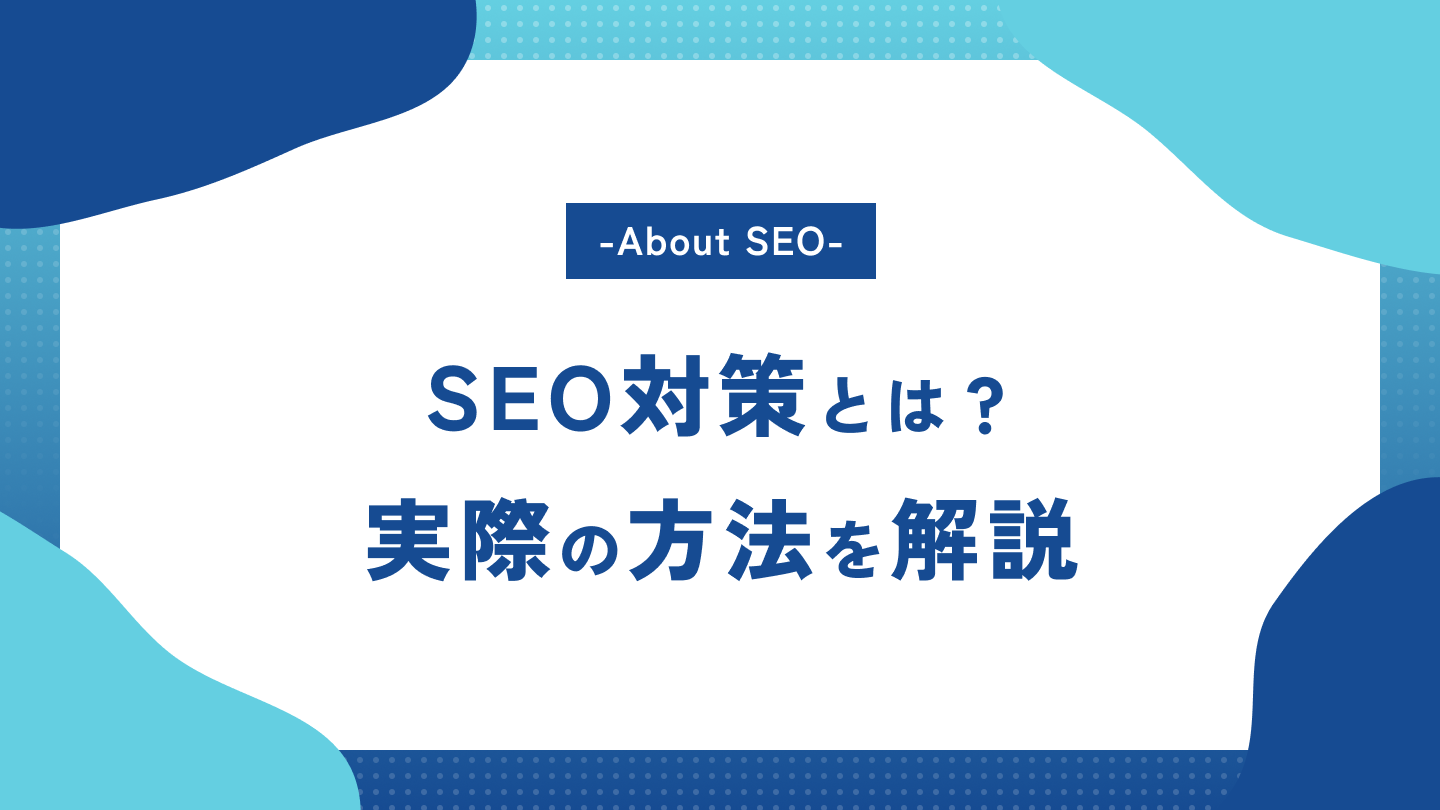なぜ今、SEO対策がビジネスに不可欠なのか?
インターネットが隅々まで浸透した現代において、顧客が商品やサービスを探す最初の接点は、多くの場合「検索エンジン」です。スマートフォンの普及により、その傾向はますます加速しています。
このような状況で自社のWebサイトが集客の役割を果たせていないとしたら、それは大きな機会損失に他なりません。
この記事では、「なぜ今、SEO対策がこれほどまでに重要なのか」という根本的な問いに答えていきます。
SEOの基本的な定義から、ビジネスにおけるメリット、そして検索エンジンがどのように情報を評価しているのかまでを掘り下げ、集客担当者として知っておくべき必須知識を解説します。

SEOとは?Web広告との違いとメリット・デメリット
まず、SEOの基本的な定義から確認しましょう。
【SEO(Search Engine Optimization)】とは、日本語で「検索エンジン最適化」と訳されます。
検索エンジンとはGoogleやSafari、Bingなど、Webにある情報を検索する際に用いられるシステムのことです。
SEOはそれらの検索エンジンで、ユーザーが特定のキーワードで検索した際に、自社のWebサイトをより上位に表示させるための一連の施策を指します。
SEOは基本的にGoogleの検索エンジンを対象に行われます。
これは日本において、Googleの検索が最も利用されているからです。
利用率は2025年3月時点で89.68%とされています。
多くの担当者様が混同しがちなのが『Web広告(特にリスティング広告)』との違いです。
両者は検索結果画面に表示される点は同じですが、その性質は全く異なります。
| 項目 | SEO(オーガニック検索) | Web広告(リスティング広告) |
| 表示場所 | 広告枠の下 | 検索結果の上部または下部の広告枠 |
| 費用 | 原則無料(※人件費やツール代は除く) | クリック課金制(表示は無料) |
| 即効性 | 時間がかかる(数ヶ月〜1年以上) | 早い(出稿後すぐ) |
| 持続性 | 施策をやめても効果はすぐには消えない | 広告費を止めると表示されなくなる |
| 信頼性 | ユーザーからの信頼性が高い傾向 | 広告と認識され、敬遠されることも |
SEOのメリット
- 長期的な資産になる:
一度上位表示されれば、広告費をかけずとも安定した集客が見込めます。良質なコンテンツは会社の「デジタル資産」となります。 - ブランディング効果が高い:
特定の分野で常に上位表示されることで、「その分野の専門家」としてユーザーに認知され、ブランドイメージと信頼性が向上します。 - クリック率が高い:
多くのユーザーは広告を避け、オーガニック検索の結果をクリックする傾向にあります。 - 潜在顧客にアプローチできる:
まだ自社の商品やサービスを知らない、課題を抱えた潜在層にもアプローチが可能です。
SEOのデメリット
- 効果が出るまでに時間がかかる:
施策を開始してから成果を実感できるまで、最低でも3ヶ月〜半年、場合によっては1年以上かかることもあります。 - 確実性がない:
Googleのアルゴリズム変動により、順位が大きく変動するリスクがあります。 - 専門的な知識が必要:
継続的な学習と正しい知識に基づいた施策が求められます。
ホームページでの集客施策を実施する場合は、Web広告の即効性と、SEOの持続性・資産性。
両者の特性を理解し、自社のフェーズや目的に合わせて使い分けることが重要です。
Googleが検索順位を決める基本的な仕組み
SEO対策を行う上で、Googleがどのようなプロセスで順位を決定しているのか、その基本的な仕組みを理解しておくことは不可欠です。
専門的で複雑なアルゴリズムが絡み合っていますが、ここではその大枠を3つのステップで解説します。
Googleは「クローラー」と呼ばれるロボットを常にインターネット上に巡回させています。
このクローラーが、世界中のWebサイトのリンクを辿りながら情報を発見し、収集します。
新しいページを作ったり、既存のページを更新したりすると、クローラーがそれを検知しに来ます。
クローラーが収集した情報は、Googleの巨大なデータベースに整理・格納されます。
これが「インデックス」です。
Webサイトはインデックスされる(インデックス登録)ことで、初めてそのページはGoogleの検索対象となります。
本棚に本を整理する作業をイメージすると分かりやすいでしょう。
ユーザーがキーワードを入力して検索すると、Googleのアルゴリズムがインデックスされた情報の中から、そのキーワードに対して「最も関連性が高く、ユーザーにとって有益である」と判断したページを瞬時に選び出し、順位付けして表示します。
このランキング決定には、200以上もの要因が複雑に関わっていると言われています。
SEO対策とは、この「クロール→インデックス→ランキング」という一連のプロセスを意識し、自社のWebサイトがGoogleに正しく、そして高く評価されるように最適化していく活動なのです。
検索ユーザーの行動とSEOの重要性
ではなぜ、検索エンジンの上位に表示されることがそれほど重要なのでしょうか?
その答えは、現代の顧客の購買行動にあります。
何か問題や欲求が生まれたとき、多くのユーザーが最初に行う行動は「検索」です。
- 「大阪駅周辺 ランチ おすすめ」
- 「法人向け 勤怠管理システム 比較」
- 「肩こり 解消法 自宅」
このように、ユーザーは自らの課題を解決するために能動的に情報を探しています。
みなさんも何か悩みがあった場合にはまず検索をしてみるという方が多いのではないでしょうか?
これは、企業側から一方的に情報を届けるテレビCMやバナー広告(プッシュ型)とは対照的な、ユーザー側から情報を求めてくる「プル型」の行動です。
ここにSEOの最大の強みがあります。
つまりSEOによって上位表示されるということは、まさに今、その情報を必要としている、購買意欲や関心度の非常に高いユーザーに、絶好のタイミングでアプローチできるということ。
この際に表示される順位が高ければ高いほど、ユーザーに見てもらえる確率は高くなります。
実は、検索結果の1位と10位では、クリック率に10倍以上の差があるというデータもあります。
| 検索順位 | クリック率 |
|---|---|
| 1 | 13.94% |
| 2 | 7.52% |
| 3 | 4.68% |
| 4 | 3.91% |
| 5 | 2.98% |
| 6 | 2.42% |
| 7 | 2.06% |
| 8 | 1.78% |
| 9 | 1.46% |
| 10 | 1.32% |
そして2ページ目以降は、ほとんどクリックされることはありません。
つまり、検索結果の上位。
特に1ページ目に表示されなければ、Webサイトは「存在しない」も同然なのです。
顧客の購買プロセスが検索から始まる現代において、SEO対策はもはや選択肢の一つではありません。
自社のビジネスを発見してもらい、顧客との最初の接点を生み出すために不可欠な、ビジネスの生命線と言えるでしょう。
STEP1:成功の鍵を握る「キーワード選定」の具体的な方法
SEO対策のプロセスにおいて、もし土台となる工程を一つだけ挙げるとすれば、
それは間違いなく「キーワード選定」です。
どれだけ質の高い記事を書き、優れたサイトを構築しても、選んだキーワードが自社のビジネスや顧客のニーズとずれていては、成果にはつながりません。
キーワード選定とは、「どのような悩みや欲求を持ったお客様に、どのWeb上の通り道(=キーワード)で出会うか」を決める、極めて重要なパートです。
このステップでは、キーワードの種類といった基本的な知識から、具体的なツールを使った洗い出し、そしてビジネスの成果に繋げるための分析方法までを体系的に解説します。
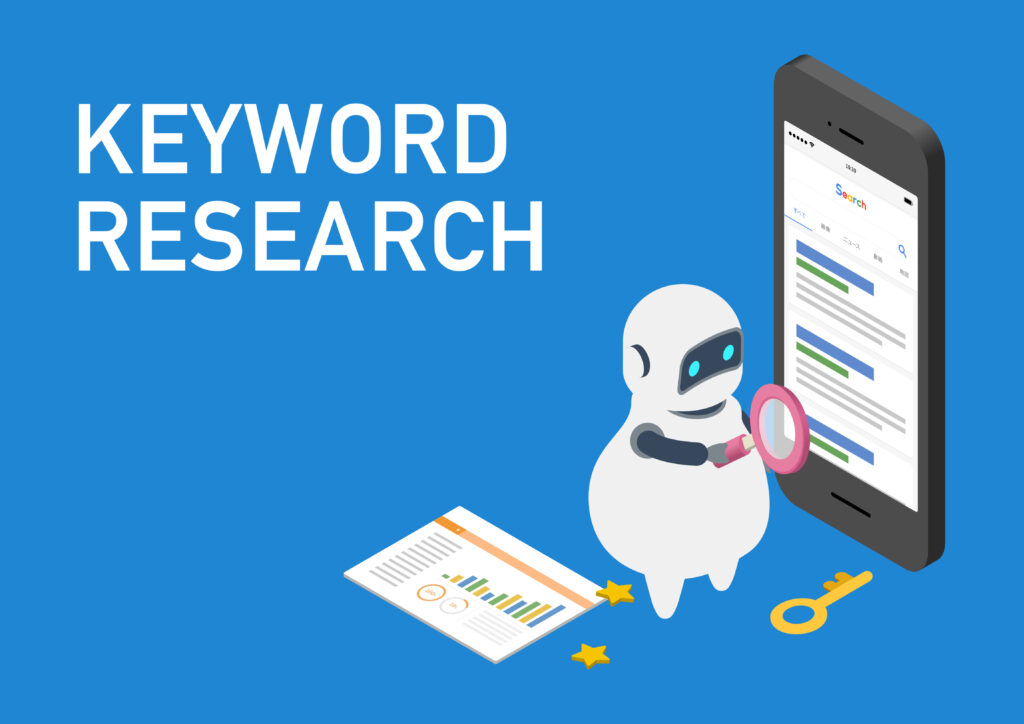
ビッグ・ミドル・ロングテール|キーワードの種類と役割
キーワードは、その検索ボリューム(月間に検索される回数)や単語数によって、大きく3種類に分類できます。
それぞれの役割を理解し、バランス良く対策することが重要です。
| 種類 | 特徴 | 具体例 | 役割と戦略 |
| ビッグキーワード | 1単語。検索ボリュームが非常に多く、競合も極めて強い。ユーザーの意図は曖昧。 | 「SEO」「マーケティング」 | サイトの最終的な目標。認知度向上には繋がるが、コンバージョン率は低く、上位表示は非常に困難。 |
| ミドルキーワード | 2語の組み合わせ。検索ボリュームは中程度で、競争も激しい。意図が具体的になる。 | 「SEO 対策」「コンテンツマーケティング とは」 | メインの集客キーワード。ここでの上位表示がアクセス数の大幅な増加に繋がるため、激戦区となる。 |
| ロングテールキーワード | 3語以上の組み合わせ。検索ボリュームは個々に小さいが、種類は無数。意図が明確。 | 「SEO 対策 初心者 方法」「コンテンツマーケティング 事例 BtoB」 | SEO初心者が最優先で狙うべきキーワード。競合が少なく上位表示しやすいうえ、ユーザーの悩みが深いためコンバージョンに繋がりやすい。 |
基本は、まずコンバージョンに近いロングテールキーワードで着実に上位表示させ、サイト全体の評価を高めながら、ミドルキーワード、そして最終的にはビッグキーワードへと挑戦していくことです。
ツールを使って自社の関連キーワードを洗い出す
では、具体的にどのようにキーワードを見つけるのでしょうか。
まずは自社の顧客になったつもりで、「自分ならどんな言葉で検索するか?」を想像することから始め、そのアイデアをツールで拡大させていきましょう。
下記にキーワード選定でよく使われるツールを挙げますので、よければ参考にしてみてください!
- Googleサジェスト機能
-
最も手軽で強力な方法です。
Googleの検索窓にキーワードを入力すると自動で表示される候補(サジェスト)や、検索結果の下部に表示される「関連性の高い検索」は、実際に多くのユーザーが検索しているキーワードの組み合わせです。
ユーザーの生のニーズがここに現れています。
- Googleキーワードプランナー
-
Google広告のアカウントがあれば無料で利用できる公式ツールです。
特定のキーワードの月間検索ボリュームを調べたり、自社のサイトURLや特定のキーワードに関連する新しいキーワードの候補をリストアップしたりできます。
SEOの基本ツールとして必ず使い方をマスターしましょう。
Google Businessキーワード プランナーで最適なキーワード選択 – Google 広告 適切なユーザーに広告を表示するために重要なのは、キーワード選びです。Google 広告のキーワード プランナーを使って、あなたのキャンペーンに合ったキーワードを選びまし… - サードパーティ製ツール
-
より高度な分析をしたい場合は、専門のSEOツールが役立ちます。
- Ubersuggest(ウーバーサジェスト):無料でも多くの機能が使え、初心者にも分かりやすいインターフェースが特徴です。
- Ahrefs(エイチレフス)、Semrush(セムラッシュ):世界中のプロが利用する高機能ツール(有料)。競合分析や被リンク調査など、本格的なSEO対策には欠かせません。
これらのツールを使い、まずは思いつく限りの関連キーワードを洗い出し、スプレッドシートなどにリストアップしていくのが最初の作業となります。
検索ボリュームと検索意図の調べ方
キーワードをリストアップしたら、次はそのキーワードで本当に対策すべきかを見極める「分析」のフェーズに入ります。
ここで重要な指標が「検索ボリューム」と「検索意図」です。
- 検索ボリューム
-
そのキーワードが月間どれくらい検索されているかを示す数値です。
キーワードプランナーなどのツールで調べることができます。
ボリュームが0のキーワードで記事を書いても誰にも読まれませんし、逆に数十万を超えるようなキーワードは競合が強すぎて上位表示が困難です。
自社のサイトの強さに応じて、月間100〜1,000回程度のボリュームを持つロングテール〜ミドルキーワードから狙っていくのが現実的です。
- 検索意図(インテント)
-
SEOにおいて検索ボリューム以上に重要なのが、この検索意図です。
これは「ユーザーがそのキーワードで検索したときに、何を知りたい、あるいは解決したいのか」という検索の裏にある目的を指します。
なお検索意図は主に以下の4つに分類されます。
Know(知りたい)
情報収集が目的。「〇〇 とは」「〇〇 方法」など。
Go(行きたい)
特定のサイトや場所へ行きたい。「〇〇 ログイン」「〇〇 店舗」など。
Do(したい)
何かをしたい、行動したい。「〇〇 とは」「〇〇 方法」など。
Buy(買いたい)
購入したい、利用したい。「〇〇 通販」「〇〇 料金」など。
この検索意図を正確に把握する最も確実な方法は、実際にそのキーワードで検索し、上位10サイトがどのようなコンテンツを提供しているかを確認することです。
Googleが上位表示させているサイトこそ、Googleが「ユーザーの検索意図を満たしている」と判断した答えそのものだからです。
競合サイトが獲得しているキーワードを分析する
自社でキーワードを探すだけでなく、競合他社がどのようなキーワードでユーザーを集めているかを知ることは、成功への近道です。
これにはAhrefsやSemrushといった有料ツールが必要になりますが、投資する価値は十分にあります。
これらのツールに競合サイトのURLを入力すると、そのサイトがどのようなキーワードで検索順位を獲得し、どれくらいのアクセスを集めているかを丸裸にできます。
競合分析によって、以下のような戦略的な発見があります。
- 自社が見落としていた、有望なキーワードが見つかる。
- 競合が力を入れている(多くのアクセスを集めている)テーマが分かる。
- 競合がまだ対策できていない、手薄なキーワード(チャンス)が見つかる。
競合を真似るだけでなく、その戦略を分析することで、自社が勝てる領域を見つけ出し、より効率的にSEO対策を進めることが可能になりますよ。

STEP2:検索意図を満たす「高品質な記事コンテンツ」の作り方
キーワードという「顧客と出会う場所」を決めたら、次は提供する高品質なコンテンツを用意するステップです。
現代のSEOにおいて、Googleが最も重視しているのは「ユーザーの検索意図にどれだけ深く、そして分かりやすく応えられているか」という一点に尽きます。
小手先のテクニックはもはや通用しません。
ユーザーの悩みを誰よりも解決する、価値あるコンテンツを作ることこそが、上位表示への唯一の道です。
このステップでは、検索意図の正しい理解から、競合に勝つための戦略立案、そして読者を惹きつけ満足させるライティングの技術まで、高品質コンテンツを作成するための全工程を具体的に解説します。
検索意図とは?4つの分類(Know/Go/Do/Buy)を理解する
コンテンツ作成において「検索意図」の理解は全ての土台となります。
検索意図とは、ユーザーがそのキーワードを検索窓に打ち込んだ背景にある「目的」のことです。
この目的を正確に理解しなければ、的外れなコンテンツを作ってしまうことになります。
検索意図は、大きく分けて以下の4つのクエリ(質問)に分類されます。
作成するコンテンツの種類は、この分類に合わせるのが鉄則です。
- Knowクエリ(知りたい)
-
情報収集を目的とした検索です。
キーワードとしては「〇〇 とは」「〇〇 方法」などが該当します。
この意図に対しては、網羅的で分かりやすい解説記事やハウツー記事を提供する必要があります。
キーワードの例:「SEO対策 とは」
- Goクエリ(行きたい)
-
特定のサイトや場所へ行きたいという明確な目的があります。
「〇〇 ログイン」「株式会社〇〇」など、指名検索が主です。
これに対しては、該当するトップページやログインページそのものが答えとなります。
キーワードの例:「LINE ログイン」
- Doクエリ(したい)
-
何か具体的な行動を起こしたいという意図です。
購入(Buy)もこの一部ですが、「資料請求」「無料トライアル」「ダウンロード」なども含まれます。
この意図には、行動をスムーズに促すためのサービスページや申込フォームが必要です。
キーワードの例:「Netflix 無料トライアル」
- Buyクエリ(買いたい)
-
商品やサービスの購入を目的とした検索です。
「〇〇 料金」「〇〇 通販」などが該当します。
この意図には、価格ページや購入ページ、導入事例などが有効です。
キーワードの例:「Ahrefs 料金」
このように記事を書く前にはキーワードの検索意図がどれに該当するのかをまず見極め、提供すべきコンテンツの形式を間違えないようにしましょう。

上位表示サイトの分析から記事のゴールを設定する
コンテンツを作り始める前に、必ずやるべきことがあります。
それは、対策キーワードで実際に検索し、現在上位表示されている競合サイトを徹底的に分析することです。
なぜなら、上位サイトは「現時点でのGoogleとユーザーの答え」だからです。
これらを分析することで、どのような情報が求められているのか、どのような切り口が評価されているのかを具体的に知ることができます。
上位5〜10サイトの見出しを全てリストアップし、共通して語られているテーマを洗い出します。これらはユーザーが最低限知りたいと思っている必須情報です。
網羅的な解説記事か、ランキング形式か、事例集か。記事のフォーマットを確認します。
図解が豊富か、専門家の監修があるか、独自のデータや事例が掲載されているかなど、他サイトとの差別化要因を探ります。
この分析結果を元に、自社が作成する記事のゴールを設定します。
そのゴールとは、「競合サイトの必須情報をすべて含み、かつ、それらのサイトにはない独自の価値(分かりやすさ、具体例、専門性など)を付加することで、検索ユーザーの満足度をNo.1にする」ことです。
ではどのようにそのゴールを達成すればいいのでしょうか?
SEOに強い記事構成案を作成する3ステップ
ゴールが決まったら、いよいよ記事の設計図である「構成案」を作成します。
構成案なしに書き始めるのは、設計図なしに家を建てるようなものです。
急いで仕上げようとするのではなく、まずはこのステップを踏んでみてください。
競合分析で見つけた「必須トピック」や、自社が提供したい「独自の価値」など、記事に含めるべき情報を箇条書きで全て書き出します。
この段階では順序を気にする必要はありません。
洗い出した情報をグルーピングし、読者が最も理解しやすい順番に並べ替えます。
一般的には、「結論(定義)→ 詳細(各論)→ 具体例 → まとめ」という流れが基本です。
ここで、どの情報をh2にし、どの情報をh3にするか、見出しの階層構造を決定します。
決定した見出し構造を元に、各見出しの下に「ここで何を書くか」を簡潔な文章や箇条書きで記述します。
この構成案がしっかりしていれば、ライティング作業の質とスピードが格段に向上します。
このような流れを経て、記事の構成を作っていきましょう。
クリックされるタイトルと分かりやすい見出しの付け方
構成案ができたら、次は検索結果画面でユーザーの目を惹き、記事の中を迷わせないための「ページタイトル」と「見出し」を考えます。
タイトルを付けるコツ
タイトルを付けるのって悩みますよね?
- キーワードを必ず含める
-
キーワードはタイトルに必ず含めるようにしましょう。
これはSEO対策においても非常に重要です。
また、キーワードはなるべく先頭に配置し、ユーザーの目につきやすくしましょう。
- 30文字前後に収める
-
タイトルが長すぎると検索結果で省略されてしまいます。
表示される文字数はデバイスによっても変わってきますが、一般的には30文字程度に収める形が良いとされています。
長すぎると
「【2025年版】SEOにおすすめの本を紹介!上位表示を目指し…」
のように途中で省略されてしまう - 内容が具体的にわかるようにする
-
数字やベネフィットなど、内容の具体性を高める文言を入れると効果的です。
「おすすめのお店3選」や「Webからのどんどん人が集まるように」など、読者が魅力を感じるようなタイトルを付けていきましょう。
- クリックしたくなる工夫をする
-
【】(隅付き括弧)を使って「【初心者必見】」のように目立たせるのもおすすめ。
カッコ内にはなるべく端的に、読者の興味を惹くような文言をいれるようにしましょう。
どのような読者に届けたいか?どのような記事なのか?を記すと効果的です。
見出し(h2, h3)の付け方のコツ
- その章の内容を簡潔に表す
-
読者は見出しを読んで、本文を読むかどうかを判断します。
目次から必要とするコンテンツを探す場合もあるため、内容を簡潔に示しておくと良いでしょう。
- キーワードを不自然にならない程度に含める
-
関連キーワードを入れるとSEO評価にも繋がります。
ただし、入れればいいというわけではありません。
いれることによって不自然にならない程度に留めておきましょう。
- 階層構造を正しく使う
-
クローラーはコードを見て、ページの構造を理解します。
この際に参考にされるのが見出しの階層構造です。
見出しは数字の大きいものから順番に入れ子になるよう設計されています。
そのため、基本的にはh2の下にh3、h3の下にh4と、優先順位に合わせてつけていくようにしましょう。
h2の下にh3を3つといったような形もOKです!
タイトルと見出しは、読者とGoogleの両方に対する道しるべです。常に分かりやすさを第一に考えましょう。
読者の満足度を高める本文ライティングのコツ
構成案と見出しに沿って、いよいよ本文を執筆します。
ここでの目標は「読者の離脱を防ぎ、最後まで読んでもらい、満足してページを閉じてもらう」ことです。
ライティング方法は様々ありますが、初めての場合にはPREP法がおすすめです。
まず結論(Point)を述べ、次に理由(Reason)、具体例(Example)、そして最後にもう一度結論(Point)を繰り返す構成です。
特にWeb記事では、読者は答えを急いでいるため、冒頭で結論を示すことが極めて重要です。
また、記事内ではなるべく専門用語は避け、中学生でも分かる言葉で書くようにしましょう。
基本的に読者は専門家ではありません。
そのため、専門用語ばかりが並んでしまうと理解しづらくなってしまい、ページを離脱する要因となってしまいます。
誰が読んでも理解できる平易な言葉を選び、専門用語を用いる場合には注釈を入れるようにしましょう。
その他、ライティングの細かい注意点は下記に記しておきますので参考にしてみてください。
- 1文は短く(60文字以内が目安)。
- 3〜4行ごとに改行して、適度な余白を作る。
- 箇条書きや表を積極的に活用する。
- 重要な部分は太字にする。
- 図解や画像を挿入し、視覚的に理解を助ける。
これらのポイントを意識することで、検索エンジンに評価されるだけでなく、読者からも「この記事は役に立った」と信頼されるコンテンツを作ることができます。
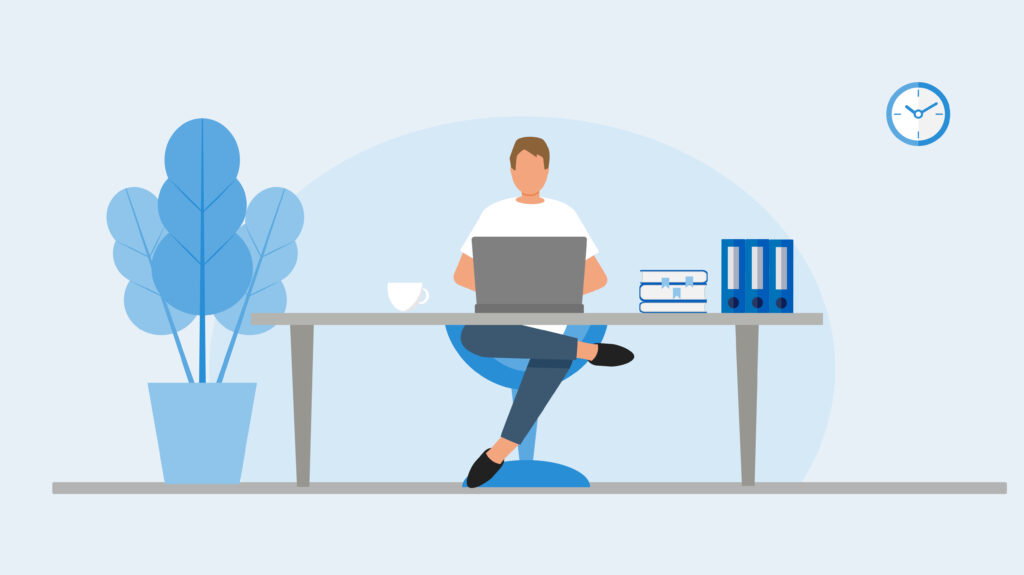
STEP3:Googleに正しく評価されるための「内部対策」10のチェックリスト
素晴らしいコンテンツを作成しても、Webサイトの構造が整理されていなかったり、Googleのロボット(クローラー)が読み取りにくい状態だったりすると、その価値は正しく評価されません。
内部対策とは、例えるなら店舗の「内装」や「案内表示」を整える作業です。
お客様(ユーザー)が快適に過ごせるように、そして店員(Google)が商品の価値を正確に把握できるように、サイトの内部構造を最適化する一連の施策を指します。
これらはWebサイトを作る際に設定する部分ですので、制作者と連携しながら対策を行うとよいでしょう。
ここでは、集客担当者として最低限押さえておくべき10の重要なチェックリストをご紹介します。
① タイトルタグ・メタディスクリプションの最適化
タイトルタグ
タイトルタグ (<title>) これは、検索結果画面やブラウザのタブに表示される、そのページの「顔」です。
SEOにおいて最も重要な要素の一つで、ページのタイトルを伝える役割があります。
制作段階でタイトルタグがしっかり設定されているかどうかを確認しておきましょう。
メタディスクリプション
メタディスクリプション (<meta name="description">) 検索結果でタイトルの下に表示される、ページの要約文です。
順位への直接的な影響はありませんが、ユーザーがクリックするかどうか(クリック率)に大きく影響します。
設定する際には下記の点に注意しましょう。
- 120文字程度で、ページの内容を的確に要約する
- 対策キーワードを含め、ユーザーの興味を惹く文章を作成する
② hタグ(見出し)の正しい階層構造
hタグ(<h1>, <h2>, <h3>…)は、コンテンツの構造をユーザーとGoogleに伝えるための「見出し」です。
STEP2で作成した構成案が正しくHTMLに反映されているかを確認しましょう。
見出しの注意点
<h1>はページの大見出しであり、1ページに1つだけ使用します。通常はタイトルと同じ内容が入ります。<h2>、<h3>、<h4>…と、必ず階層の順番を守って使用します。<h2>の次にいきなり<h4>を使うといった階層の飛ばしはNGです。- 見出しタグは、単なる文字の装飾ではなく、文章の構造を示すために正しく使い分けます。
③ 画像のalt(オルト)属性設定とファイル軽量化
alt属性について
Googleのクローラーは画像を視覚的に「見る」ことができません。
alt属性に画像の内容を説明するテキストを入れることで、Googleに画像が何であるかを伝えることができます。
また、通信環境によって画像が表示されない場合に代替テキストとして表示されたり、音声読み上げソフトで利用されたりします。
- 画像の内容を簡潔に説明する
- 関連するキーワードを不自然にならない程度に含める
ファイルの軽量化について
ページの表示速度はSEOに大きく影響します。
重い画像ファイルは、ページの表示速度を遅くする最大の原因です。
iPhoneなど、最近のスマートフォンは画質が良くなっている分、一枚あたりの画像サイズも大きくなっています。
そのため、アップロードする際には画像サイズを小さくするなど、必ず軽量化するようにしましょう。
TinyPngなどの圧縮ツールを使うのも便利でおすすめです。

④ ユーザーとクローラーを導く内部リンク戦略
内部リンクとは、自社サイトのあるページから別のページへ設置するリンクのことです。
ユーザーにとっては関連する情報へスムーズに移動でき、サイト内の回遊性が高まるため、ページの閲覧数や滞在時間を増やすことができます。
これらはSEOでも重要視されている部分であるため、意識するようにしておきましょう。
また、内部リンクを設置することでページ同士の関連性を伝え、重要なページを認識させる手がかりとなります。
- 末尾に「この記事もおすすめ」のような関連記事を設置
- 途中に「詳しくはこちら」のように参考記事を設置
のようにリンクを付けておくことで、記事の補足や閲覧数を増やすことができます!
⑤ モバイルフレンドリー(スマホ対応)の重要性
現在、GoogleはWebサイトを評価する際にPCサイトではなくスマートフォンサイトを主に見る「モバイルファーストインデックス」を完全導入しています。
つまり、スマートフォンで見たときにサイトが使いにくい(文字が小さい、リンクが押しにくいなど)場合、SEO評価が著しく低くなる可能性があります。
自社のサイトがスマホ対応しているか、Googleの「モバイルフレンドリーテスト」で確認しましょう。
⑥ サイトの表示速度を改善する方法
ページの表示速度は、ユーザー体験に直結するため、Googleのランキング要因になっています。
「3秒以上かかると半数以上のユーザーが離脱する」というデータもあるほど重要な部分です。
主に下記の点に注意すると良いでしょう。
- 画像の軽量化
- サーバーの応答速度の改善
- 不要なコードの削除
- 不要なコンテンツの読み込み制限
表示速度はGoogleの「PageSpeed Insights」でサイトのURLを入力すれば、速度のスコアと具体的な改善点を確認できます。
PC版とスマホ版でそれぞれ測定でき、改善点も表示されるためぜひ確認してみてください。
⑦ 分かりやすいURL(パーマリンク)の設定
URLは、ユーザーがページの内容を理解する手助けをします。
- 良いURLの例:
https://example.com/service/seo-taisaku - 悪いURLの例:
https://example.com/page?id=123
短く、シンプルで、そのページの内容を表す単語で設定するのが理想です。
日本語でも設定することはできますが、実際には文字コードに変換されてしまい、後から読みづらくなってしまうため、基本的には英語で設定するようにしましょう。
⑧ XMLサイトマップの作成と送信
XMLサイトマップとは、Googleのクローラーに対して「サイト内にこのようなページがあります」と知らせるためのサイト全体の地図のようなファイルです。
これをGoogleサーチコンソールから送信することで、クローラーがサイトのページを漏れなく、効率的に発見する手助けをします。
また、サーチコンソールを用いれば、インデックス登録を申請することもできますので、なかなか検索結果に表示されない場合は申請するようにしましょう。
⑨ パンくずリストの設置
パンくずリストとは、Webサイトの階層構造を視覚的に示したリストのことです(例: HOME > ブログ > SEO > 内部対策 )。
これにより、ユーザーがWebサイトのどこにいるのかが把握しやすくなります。
また、Googleがサイトの構造を理解する手助けにもなるため、忘れず設定しておくようにしましょう。
⑩ SSL化(https)の確認
SSL化とは、サイトの通信を暗号化することです。
URLが http:// ではなく https:// から始まっているサイトがSSL化されているサイトです。
http://の場合には暗号化がされていないため、お問い合わせや決済などでユーザー送信した情報が第三者に盗み見られてしまう恐れがあります。
加えて、SSL化は検索順位に影響すると発表されています。
また、SSL化が行われていないサイトでは「保護されていない通信」と警告が表示されるため、ユーザーに不安を感じさせないためにも必ず行うようにしましょう。
STEP4:サイトの信頼性を高める「外部対策(被リンク)」の基本
これまでのステップで、キーワードを選定し(STEP1)、高品質なコンテンツを作り(STEP2)、サイト内部を整えました(STEP3)。
最後のステップは、サイトの「信頼性」と「権威性」を外部から高めるための外部対策です。
外部対策の核となるのが「被リンク」の獲得です。
被リンクとは、他のWebサイトから自社のサイトに向けて設置されたリンクを指します。
Googleは、被リンクが多ければ、そのページは「多くのWebサイトから参考にされている高品質なページ」なのではないかと推測します。
質の高いサイトから多く参照されているサイトは、それだけ価値があり信頼できると判断され、検索順位が向上する傾向にあります。
しかし、ただ被リンクを増やせばいいというわけではありません。
かつては被リンクの「量」が重視された時代もありましたが、現在のGoogleは「質」を極めて重要視します。
本章では、ペナルティのリスクを避け、サイトの評価を健全に高めるための、被リンクの基本的な考え方と手法を解説します。

外部対策(被リンク)が今も重要な理由
Googleのアルゴリズムは日々進化していますが、被リンクが重要なランキング要因であることは今も変わりません。
その理由は、被リンクが「第三者による客観的な評価」を示す指標だからです。
自分で「この記事は素晴らしい」と言うのは簡単ですが、全く関係のない第三者が「この記事は素晴らしいので、ぜひ読んでみてください」と紹介してくれれば、その情報の信頼性は格段に高まります。
Googleの考え方もこれと同じです。
- 関連性の高い、権威あるサイトからの被リンクは、そのページの専門性や信頼性を裏付ける強力な証拠
- 多くの質の高いサイトからリンクされているコンテンツは、それだけ多くの人にとって価値がある「良いコンテンツ」である可能性が高い
このように、被リンクはコンテンツの質を外部から担保し、サイト全体のドメインパワー(サイトの信頼性)を引き上げる上で、依然として非常に重要な役割を担っているのです。
質の高い被リンクと低品質な被リンクの見分け方
重要なのは、どんなリンクでも良いわけではないという点です。
低品質な被リンクは、評価されないばかりか、ペナルティのリスクさえあります。
そのため、良い被リンクと悪い被リンクを正しく見分けることが不可欠です。
高品質な(良い)被リンクの例
- 関連性の高いサイトからのリンク
-
例:Webマーケティング会社のブログから、自社のSEO解説記事へのリンク
- 権威性の高いサイトからのリンク
-
例:官公庁(.go.jp)、大学などの教育機関(.ac.jp)、大手メディアなどからのリンク
- 自然に紹介されているリンク
-
例:「このテーマについては、〇〇社の記事が非常に参考になります」といった文脈で自然に設置されたリンク
- アクセスのあるページからのリンク
-
例:多くの人が訪れる人気のページからのリンク
低品質な(悪い)被リンクの例
- 関連性が全くないサイトからのリンク
-
例:海外のペット紹介サイトから日本のBtoBサービス紹介ページへのリンク
- 低品質なリンク集サイトからのリンク
-
例:ただリンクを貼ることだけが目的の、内容の薄いサイトからのリンク
- 自作自演のサイト群からのリンク
-
例:自身で作成した複数のサイトからの自演リンク
- Googleのガイドラインに違反する購入したリンク
-
例:購入したリンクからの被リンク
このように被リンクといってもただ貰えればいいというわけではありません。
その被リンクがもしも悪いリンクの場合、ページの評価を良くしてしまうどころか、最悪の場合下げてしまいます。
自身でつけようとするのではなく、質の高いコンテンツを提供し続け、自然に集まるようにしていきましょう。
自然な被リンクを獲得するための考え方と手法
では、どうすれば質の高い被リンクを「自然に」獲得できるのでしょうか。
その根本的な考え方は、「リンクを増やす作業(ビルディング)」ではなく、「リンクをされたくなる価値を提供した結果、自然に集まる(アーニング)」というマインドセットを持つことです。
その上で、獲得の可能性を高める具体的な手法をいくつかご紹介します。
- ① 唯一無二の「一次情報」コンテンツを作成する
-
被リンク獲得において最も王道で強力な手法です。他にはない、自社だからこそ発信できる情報を作ることができれば、多くのサイトが引用元としてリンクを貼ってくれます。
- 独自の調査データやアンケート結果
- 詳細な導入事例やお客様インタビュー
- 業界の課題に対する専門家としての深い考察
- ② 分かりやすい図解やインフォグラフィックを作成する
-
複雑な情報を一枚の図やイラストにまとめたコンテンツは、他のブログやメディアが「分かりやすい資料」として引用・転載しやすく、被リンクに繋がりやすい傾向があります。
- ③ プレスリリースを配信する
-
新サービスの開始、画期的な研究開発、大規模なイベントの開催など、社会的なニュース価値がある情報をプレスリリースとして配信します。
それを見たWebメディアがニュースとして取り上げてくれれば、質の高い被リンクを獲得できます。
やってはいけない!ペナルティ対象となるNGな被リンク対策
最後に、絶対に手を出してはいけない、Googleのガイドラインに違反する行為を改めて確認します。
これらの行為は、一時的に順位が上がったとしても、Googleに見つかれば順位の大幅な下落や、最悪の場合インデックス削除といった重いペナルティを課せられます。
- ① リンクの購入
-
金銭を支払ってリンクを設置してもらう行為は、最も代表的なガイドライン違反です。
- ② 過剰な相互リンク
-
「相互リンクしましょう」とだけ持ちかけ、関連性の低いサイトと大量にリンクを交換する行為。
- ③ 自作自演のサテライトサイト
-
被リンクを送ることだけを目的に作られた、内容の薄い複数のサイトを自分で作り、そこからメインサイトにリンクを送る行為。
- ④ 自動プログラムによるリンク設置
-
ツールを使い、海外のブログのコメント欄などに自動で大量のリンクをばらまく行為。
「簡単・大量・安価」に獲得できるリンクは、ほぼ全てが低品質で危険なリンクだと考えましょう。
また、SEO対策業者の中には、これらの違反行為を用いて一時的にランキングを上げて一時的に成果が出たように見せかける業者も残念ながら存在します。
そのため、外部に依頼する場合には注意が必要です。
委託先を選定する際にはどのような方法を用いるかしっかり調査したうえで決めるようにしましょう。

必須ツール!Googleアナリティクスとサーチコンソールの使い方
SEOは施策を実行して終わりではありません。
その結果をデータで正しく把握し、次の改善に繋げる「効果測定」のプロセスが不可欠です。
そのための最も強力な武器が、Googleが無料で提供する「Googleアナリティクス」と「Googleサーチコンソール」です。
この二つのツールは、車の両輪のような関係です。
- Googleサーチコンソール
-
ユーザーがサイトを訪れる前の動き(Google検索での表示回数、順位、クリック率など)を把握するツール。
- Googleアナリティクス
-
ユーザーがサイトを訪れた後の動き(どのページを見たか、滞在時間、コンバージョンに至ったかなど)を把握するツール。
両者を連携させて使いこなすことで、SEO施策全体の成果を正確に可視化し、データに基づいた戦略的な改善が可能になります。
Googleアナリティクスで見るべき基本指標とレポート
Googleアナリティクス(現行バージョンはGA4)は、サイトに訪れたユーザーの行動を詳細に分析できます。
見るべき指標は無数にありますが、まずは集客担当者として特に重要な基本指標とレポートに絞って確認するのが基本です。
Googleアナリティクスではアクセスしたユーザーの行動をレポートにまとめてくれているため、それらを参考にユーザーの分析を行えます。
例えばユーザーが「どこから」来たのかはレポート > 集客 > トラフィック獲得から確認可能です。
その他にも、SEOの成果を測るにはチャネルグループの中の「Organic Search(自然検索)」のセッション数やユーザー数、コンバージョン数などの基本指標を確認します。
代表的な基本指標については下記を抑えておきましょう。
- ユーザー数
-
サイトを訪れたユニークな人数。
同じユーザーが訪れたとしてもカウントは増加しません。ただし、ユーザーがクッキーをオフにしていた場合はカウントされてしまうため注意しましょう
- セッション数
-
サイトへの訪問回数。
- エンゲージメント率
-
訪問全体のうち、ユーザーが何らかの関与(10秒以上の滞在、2ページ以上の閲覧、コンバージョンなど)を行ったセッションの割合。この数値が高いほど、質の高いアクセスであると言えます。
- コンバージョン数
-
設定した目標(商品購入、問い合わせ、資料ダウンロードなど)を達成した回数。
SEOの最終的な成果を測る最も重要な指標です。
これらの数値が伸びていれば、SEO施策が上手くいっている証拠です。
Googleアナリティクスではサイトに関する分析を数値で確認できるため、PCDAを回す際に非常に役立ちます。
ぜひ積極的に活用していきましょう!
Googleサーチコンソールの登録方法と主な機能
Googleサーチコンソールは、Google検索におけるサイトのパフォーマンスを監視し、問題を解決するためのツールです。
主に下記のことが実施できます。
- 検索パフォーマンスの確認
-
SEO担当者が最もよく使う機能です。
特定のキーワードやページが「何回表示され(表示回数)」「何位に表示され(平均掲載順位)」「何回クリックされたか(クリック数、CTR)」を詳細に分析できます。
施策の成果を最もダイレクトに確認できる場所です。
- ページのインデックス登録
-
サイト内のページが、正しくGoogleに認識(インデックス)されているかを確認できます。
重要なページがインデックスされていない、エラーが出ているなどの問題を発見し、修正を促すことができます。
- サイトマップの送信
-
作成したXMLサイトマップをここに送信することで、Googleにサイトの構造を効率的に伝え、クロールを促進します。
検索順位やクリック率を分析してリライトに活かす方法
サーチコンソールのデータは、コンテンツを改善(リライト)するための宝の山です。
「検索パフォーマンス」レポートを使い、以下の2つのパターンに注目することで、改善すべきページを効率的に見つけ出すことができます。
パターン1:表示回数は多いのに、クリック率(CTR)が低いページ
- 状態
-
多くのユーザーの検索結果に表示されているが、クリックされていない状態です。平均掲載順位が10位以内なのにCTRが極端に低い場合などが該当します。
- 課題
-
検索結果に表示される「タイトル」と「メタディスクリプション」に魅力がなく、競合にクリックを奪われている可能性が高いです。
- 改善策
-
STEP3で解説したポイントを元に、より具体的で、ユーザーの興味を惹き、クリックしたくなるようなタイトルとディスクリプションに修正します。
パターン2:平均掲載順位が11位〜20位のページ
- 状態
-
検索結果の2ページ目に位置し、「あともう一歩」で上位表示を逃している状態です。Googleからは一定の評価を得ていますが、何かが足りていません。
- 課題
-
コンテンツの網羅性や専門性、分かりやすさが、上位10サイトに比べてわずかに劣っている可能性があります。
- 改善策
-
再度そのキーワードで上位10サイトを分析し直し、自社のコンテンツに不足している情報(トピック)を追加したり、最新の情報に更新したり、図解や具体例を加えて分かりやすくするなどのリライトを行います。
このようにデータを活用して仮説を立て、改善を繰り返す(PDCAサイクルを回す)ことこそが、SEOを成功に導くための最も確実な方法です。
まとめ:継続的なSEO対策で集客を成功させるために
ここまで、SEO対策の全体像を4つのステップと効果測定のツールに分けて解説してきました。
キーワードで方向性を決め(STEP1)、ユーザーの役に立つ最高のコンテンツを作り(STEP2)、サイトを快適で分かりやすい場所に整え(STEP3)、外部からの信頼を獲得する(STEP4)。
そして、その全ての結果をデータで検証し、次の一手へと繋げる。
この一連の流れは、一度やれば終わりというものではありません。
SEOとは、ビジネスの成長と共に継続的に行う、長距離走のようなものです。
最後に、この長い道のりを着実に走り抜き、集客というゴールを達成するために不可欠な「期間の目安」「日々の改善サイクル」、そして「担当者としての心構え」についてお伝えします。
SEO施策の効果が出るまでの期間の目安
担当者として、経営層から「いつ成果が出るのか?」と最もよく問われる質問かもしれません。
広告とは異なり、SEOは即効性のある施策ではありません。
事前に現実的な期間の目安を共有しておくことが非常に重要です。
サイトの技術的な問題(内部対策)を修正し、キーワード戦略に基づいて初期のコンテンツを投入する時期です。
Googleがサイトの変化を認識し始める段階で、目に見える成果はほとんど出ません。
投入したコンテンツがインデックスされ、一部のロングテールキーワードで順位がつき始める時期です。
サーチコンソール上の表示回数やクリック数が、徐々に右肩上がりのグラフを描き始めます。
継続的なコンテンツ投下と改善によりサイト全体の評価が高まり、ミドルキーワードでも上位表示されるページが出始めます。
オーガニック検索からの流入が、事業に貢献する安定したチャネルとして機能し始めます。
もちろん、これはあくまで一般的な目安です。
サイトの既存の強さや、競合の激しさ、投入するリソースの量によって期間は変動します。
大切なのは、短期的な結果を求めず、長期的な視点で腰を据えて取り組むことです。
日々の順位チェックと改善(PDCA)の回し方
SEOは「実行したら終わり」ではなく、「実行→分析→改善」のサイクルを回し続けることで成果が最大化します。
これはビジネスフレームワークであるPDCAサイクルそのものです。
- Plan(計画)
-
キーワード選定やコンテンツの企画を行います。
ターゲットとするユーザーは誰で、どのような情報を提供すれば満足してくれるかを計画します。(STEP1, 2)
- Do(実行)
-
計画に基づいて、コンテンツの作成・公開や内部対策・外部対策を実行します。(STEP2, 3, 4)
- Check(評価)
-
公開したコンテンツや施策の結果を、サーチコンソールやアナリティクスで分析します。
順位はついたか? 流入は増えたか? コンバージョンに繋がっているか? を客観的なデータで評価します。
- Action(改善)
-
評価の結果を元に、改善策を立案・実行します。
クリック率が低いページのタイトルを修正したり、順位が伸び悩む記事に情報を追記してリライトしたりします。
そして、この改善の結果を元に、また次の「Plan」へと繋げていきます。
PDCAはマーケティングの基本です。
日々の順位変動に一喜一憂するのではなく、週次や月次でデータを評価し、このPDCAサイクルを愚直に回し続けることで成果へとつなげていきましょう。
SEO担当者が常に意識すべきこと
最後に、SEO担当者として最も大切にしてほしい、普遍的な心構えを3つお伝えします。
常に「ユーザーファースト」であること
Googleのアルゴリズムは日々変化しますが、「ユーザーにとって最も価値のある情報を提供したい」というGoogleの理念は決して変わりません。
小手先のテクニックでGoogleを騙そうとするのではなく、常に検索ユーザーの方を向き、彼らの悩みや疑問を誰よりも深く解決するコンテンツは何かを問い続けてください。
それこそが、あらゆるアルゴリズム変動にも揺るがない、最強のSEO対策です。
SEOはマーケティング活動の一部であること
SEOを孤立した施策と考えず、SNS、メルマガ、広告、営業活動など、会社全体のマーケティング活動の一部として捉えましょう。
SNSで話題になったトピックを記事にしたり、営業担当者が顧客からよく聞かれる質問をコンテンツにしたりすることで、施策の相乗効果が生まれます。
最新情報を追いかけつつ、本質を見失わないこと
SEOの世界は変化が激しいため、Googleの公式発表や信頼できる情報源から最新の動向を学ぶ姿勢は重要です。
しかし、細かな変動に振り回される必要はありません。
ユーザーのために高品質なコンテンツを作り、サイトを使いやすくするという本質的な部分を徹底していれば、恐れることはありませんよ!

最後に
こつこつとコンテンツを提供していき、Webサイトというデジタル資産を着実に育てていく。
このようにSEO対策は、時間がかかる地道な作業です。
大変ではありますが、将来的には大きな成果へと繋がります。
このガイドが、皆様のビジネスを長期的に成長させる一助となれば幸いです。
運用を行ったうえでわからないこと等がございましたら、お気軽にご相談ください。
最後まで御覧いただきありがとうございました。